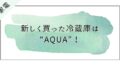こんにちは。らぶこです。
今回は、図書館の「哲学・宗教」の本棚を通り過ぎようとした時に、ふっと目に飛び込んできた本「しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久」を記録したいと思います。
ここ最近「自分の幸せって、なんだろう?」とずっとモヤモヤしていた中での不思議な出会いで、パラパラ読んでみると「これは何かのヒントになるかも」と直感があったので、借りてきました。
すぐ他人と比較してしまう
自分に自信がない
「普通は…」が口癖
もっと物事がスムーズに進めば楽になれると思う
幸せを追い求めることに疲れた
…といったことに日々モヤモヤしている方がいらっしゃったら、今回の図書を読むとそのキューッ!!!となっている心をいくらか解きほぐされるような言葉や考え方で楽になれるのでは、と思います。
「何がわかる本?」が先に気になる方は、この後のポイント3選をご参考ください。
後半は私の同書からアハ体験を受けて考え方や捉え方に衝撃の変化を起こしたエピソードを記録したいと思いますのでご興味がおありの方はぜひご参考ください。
この図書記録が少しでもどなたかの、何かのお役に立つことができたら嬉しいです!
「しあわせる力」のポイント3選
まずは、簡単に同書のポイント3つをご紹介します。
「しあわせ」は動詞であり、行動と関係性の中にある
著者は、「しあわせ」を静的な「状態」ではなく、動的な「行動」として捉えており、しあわせとは「自ら幸福を作り出し、他者と関係性を結ぶ中で育む力」であると説いています。
禅の教えでは「今ここ」に集中し心を尽くすことで充足感を得ることが重要、とされています。
また幸福は自己完結するのではなく、“他者や自然とのつながり”によって実現されるものである、と主張。
「足るを知る」心の大切さ
「幸福の条件は物質的な豊かさ・目標の達成ではない」と強調しています。
禅の教えにある「足るを知る」という言葉の通り、自分にとって本当に必要なものを見極め、それを受け入れることで満たされた心を持つことが幸福の基盤になると説いています。
「もっと欲しい」という欲求を抑え、今あるものに感謝し満足することで、心の平穏を得られると主張。
思考を手放し、ただ生きることの価値
現代人は過剰な思考にとらわれがちで、それが不安や焦りを生む原因となっている、と主張する著者。
禅的幸福論では“思考”を手放し、身体感覚や行動に意識を向けることが勧められています。
瞑想や日々の作務(禅における労働や行動)を通じて、無心の境地に至り、「ただ生きる」ことの尊さを体感することで、深い幸福を得られるとしています。
いかがですか?
上記だけでも、日々の仕事・家事・育児に追われる生活を振り返ると「はっ!」とすることが多くないですか?(私は読み進める間に何度もアハ体験をしました;)
同書を通じて著者/玄侑宗久氏は、幸福を「日々の行動と意識の中で実践するもの」として捉えるとよいと訴えており、禅的なシンプルな考え方が現代社会の複雑さに対する処方箋になることを提示されています。
読書中のアハ体験

ここからは同書を読み進める中で得たアハ体験(※)により、従来の考え方・捉え方が衝撃的にガラッと変化したことを記録していこうと思います。
※アハ体験とは:ひらめきや気づきの瞬間に「あっ!」と感じる体験、または「わかったぞ」という体験
「幸せ」「幸福」の定義は社会に洗脳されていたものだった?
同書冒頭から、「エッ!」と衝撃が走りました。
著者は「しあわせ」と聞いたらどんな文字を思い浮かべるか?と問われるのですが、私は迷わず「“幸福”でしょ」と思いました。
しかしどうやら、明治時代に英語「Happiness」の訳語として“幸福”と当て字され、近代西欧の”計量できる幸福”という考え方が日本に侵入してきたんだ、とのことです。
十八世紀後半、ジェレミー・ベンサムというイギリスの哲学者が「最大多数の最大幸福」という考え方を示し、幸福計算という具体的な方法も示しました。大きさや長さや近さ、速さなどの基準で、幸福は快楽と同じように軽量できると提案したのです。それ以来、幸福の主流は数値化できるものになりました。[しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久より]
では、その前に日本独自に持っていた「しあわせ」とはどんな定義だったのか。
同書によれば、奈良時代に起こったこの言葉の当て字は「為合(しあ)わせ=私がすることと、誰かのすることが合わさること」とされ、室町時代には「仕合(しあ)わせ=人と人との関係がうまくいくこと」という意味に変化していったそうです。
この時点で、日本人が考えてた「しあわせ」の定義は「人間関係からつくり上げられるもの」のため、西洋の「数値で測れるもの」とは大きく異なっていますね。
冒頭でもあった私の “ここ最近「自分の幸せって、なんだろう?」とずっとモヤモヤしていた”は、この西洋的考え方の数値的幸福が“真の幸福なのか?”と疑問視していたからか、と素直に捉えることができました。
私のモヤモヤは、年収・所持しているブランド品の数や値段・自由時間などを他人と比較して落ち込んでいる状態で、定義するなら全て「数値的幸福」でした。
しかしどうでしょう?
「人間関係からつくり上げられるもの」「数値で測れないもの(プライスレス)」なものが本来は“しあわせ”??
とすると、
「愛する家族と一緒に過ごしてる、毎日何かしら笑ってる、病気していない、毎日衣食住にも困っていない」…おや?もうすでに持ち合わせているのでは??と拍子抜け。
と同時に、あまりにも自然にスッと腑に落ちました。
幸せの定義を違う見方にするだけで、こんなにもモヤモヤがなくなるなんて…!というアハ体験でした。
余談:
昨今流行りの「◯◯サロン」や「○◯コミュニティ」とやらも、時間・場所・手間を省いた便利なものを追求しすぎる社会の中で「実際に人間(他人)と繋がれる居場所・自分を受容してくれる人間関係を構築できる場」を求める人がたくさんいる、ということの表れなのかな?と妙に納得してしまいました。
(従来私はなんでこんなにみんな他人とツルみたがるんだろう…とだいぶ捻くれた目線で傍観していました;)
現代社会には“自分を信じる力”が必要
同書の後半に「しあわせは自分を信じることから(p166)」の項目があります。
そこには、以下のような印象的且つ心に響いたフレーズがあったのでご紹介します。
自分の中には七福神のような七癖が潜んでいる。
(略)
七人七様、相手に応じて出てきてもらって気持ちをパタパタと変えて、自由に活発に生きる。そのように考えられれば、常に相手や状況に「仕合わせ」やすい。しあわせを感じやすいのではないでしょうか。[しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久より]
自分に潜んでいる無限の力を信じることがものすごく重要になってくるわけです。
(略)
「私はこうゆう人間です」と決めつけたり、自分をロジカルに切り取って個性を重視しすぎたりすることは、「信じる」ということと全く関係のない世界の話です。何が出てくるかわからない自然の分身である自分を、そのまま信じるということが大切だと、禅は考えているのです。[しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久より]
実際、何が印象的だったのか。
私にとっては「自分の強みの集合体=個性」と(勝手に)定義づけていたので、上記の「自分をロジカルに切り取って個性を重視しすぎることは信じることではない」というフレーズにはエッ!;となりました。
要は、「七人七様(ポジティブ&ネガティブ)をそのまま信じることが大事」で、「強みばかりが個性ではない」ということです。(この衝撃は私だけでしょうか…?w)
巷では「土の時代は終わり。これからは風の時代」というような「個性を活かせた者勝ち」な世界がきているようです。(根拠がなんなのか不明ですが)
現代社会では「私を生きよう」とか「個性を尊重しよう」などど至るところで見たり聞いたりと一見ポジティブな風潮がありますが、どうしても「個性=強み」と捉えてしまいがちな気がします。しかし反対の「弱み=捨てていくもの?克服していくもの?」と、迷子になりませんか?それゆえに、どんどん個性を見つけないと!伸ばしていかないと!と苦しくなってきませんか?(私がそうでした;)
しかし同書の以下の言葉が、その苦しさを一気に解き放ってくれた気がします。
(略)「自分を信じる」ということは、自分のことなんか自分でもわかっちゃいないよ、ということです。わからないまま安心していられるのが、じつは信じるということなのです。わからないまま進むから、奇跡だって起こるわけです。[しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久より]
(…あ、なーんだ。
確かに“私”といっても、過去の経験からすると“認識できる限りの私”なんだろうし、内観ノートとかで自分を理解した気にもなってたけど全部をわかっているか?と言われると…わかんないなぁ。笑
天使でも悪魔でも、そのままひっくるめて私、でいいのかー。笑)
素直にこんな感想を持てました。単純です。
同時に、心の状態が悪かった時代にスピリチュアル界隈の記事や動画などから徐々に自分を取り戻してきた私からすれば、何かに悩んだ時には「禅の考え方を学んだら全方位うまくいく・解決するのでは?」と思ってしまいました。スピリチュアルより、禅の方が地に足ついた考え方かもしれません。(個人的意見です)
まとめ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます!
最近直感が冴えているのか、ふっと目に入ってきたもの・思い付いたことが、ちゃんと今の自分に必要なことになる事象が続いています。(嬉しいような、ちょっと怖いような)
今回の図書「しあわせる力 禅的幸福論/玄侑 宗久」も、現代社会の無意識に持っていた偏った見方から、「しあわせの本質」を考えるきっかけになったので、必要な出会いだったと思っています。
テレビやSNS(特にインスタ、FB)を辞めてからだいぶ心が楽になったと思っていましたが、まだまだ“自分を信じる力”を鍛える伸びしろはあるな〜と感じました。(No自己否定、がモットー)
不安を煽るような情報うんざりしていたり、幸せ探し迷子になっていらっしゃる方がいらっしゃったら、同書は時が止まるような平穏な言葉や考え方が詰まっていて心を癒してくれる本かと思いますので、ぜひ読んでみてほしいです。
それでは、enjoy!
▼今回の図書(再掲)


![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/44ec735a.565ff22e.44ec735b.3ebb0abf/?me_id=1273418&item_id=12742051&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fvaboo%2Fcabinet%2Fbooks115%2F9784047315129.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)